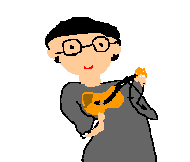
弦楽器の基礎知識
ミツマ・ミュージックプロダクツ副社長宮原勅治・監修
日本弦楽器製作家協会会員
イチイヒロキ・著
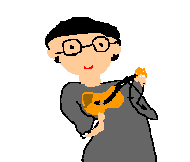
このページはミツマ音楽通信の中のから、弦楽器奏者のために弦楽器の取り扱いについて、 書かれていたページをまとめたものです。
| Vol. 7 | 1994. 8. 8発行 | ニス |
| Vol. 8 | 1994. 10. 8発行 | 魂柱 |
| Vol. 9 | 1994. 12. 1発行 | 魂柱その2 |
| Vol. 10 | 1995. 3. 20発行 | 駒 |
| Vol. 11 | 1995. 8. 12発行 | 弦の話 |
| Vol. 12 | 1996. 1. 10発行 | にかわ 楽器の接着剤 |
| Vol. 13 | 1996. 6. 25発行 | 楽器の調整 |
| Vol. 14 | 1996. 12. 10発行 | ラベルのはなし |
| Vol. 15 | 1997. 4. 15発行 | 楽器のねだん その1 |
| Vol. 16 | 1997. 8. 6発行 | 楽器のねだん その2 |
弦楽器の質問箱 (メールで質問をお寄せください)

弦楽器は、ヨーロッパの長い歴史と文化のもとで発展してきました。私はフィレンツェでヴァイオリン製作をしていましたが、高級な古い家具の修理などの仕事も頼まれたことがあり、ヴァイオリンの頭の形やf孔のデザインと家具との親密性を感じたことが多くあります。美しい曲線によって作られたテーブルの回りにパフリングの入った物や、幸運にも保存されていた17世紀の北イタリアの家具の中に健康状態の良いストラディヴァリのニスと同じような物を見かけたりもしました。古い楽器が当時の家具作りと同じ技術によって作られていたわけです。ところが近代の木工工芸品などは工場で大量に安く作られ、多くの仕事は機械によってなされ、接着剤、吹き付けの堅牢なニスが多用されています。
ニスに関して書くなら本が一冊書けるので、今それについて詳しくは述べませんが、ストラディヴァリが使っていた時代のニスは年月とともに酸化してしまって、現代の発達した科学を使っても解明することはまだできないのです。しかしなぜその後そのニスが使われなくなったのかに関して、一つ理由があります。18世紀のはじめ頃シェラック (gomma lacca 伊) という樹脂が輸入されはじめ、ヨーロッパの間でも使われ始めました、なぜならば以前に使われていたニスより使いやすく丈夫で、値段も安かったからです。18世紀から19世紀にかけての楽器作りや家具屋にとっては、大変便利だったわけです。不幸にも18世紀の半ばからクレモナでもこのニスが使われはじめ、たくさんの楽器が台無しになってしまいました。ニスは年月がたつにつれて変化していきますし、材木も乾燥してきます。できたときに良くても200年後のニスによる弊害を予測するのは困難だったのでしょう。楽器作りがそのことに気づいたときには、もうおそかったわけです。
おわかりになったと思いますが、楽器は敬意ある歴史と文化の遺産です。300年前の技術で楽器が未だに作られているのは、それなりの理由があるのです。楽器は、掃除一つにしても現代の家具と同じようにはできないです。楽器のニスは大変デリケートです。ウイスキーの一滴でもニスを損なうことがあります、洗剤などは絶対使わないで下さい。化粧品に使用されている成分にもニスに影響を与えるものが多く使われています。熱にも弱いです。暑いところに置いておくとニスが溶けたりします。急激な温度や湿度の変化にも気を付けてください、割れやはがれの原因の一つです。特に日本の夏は湿度が高いので注意が必要です。
と言うわけで次回から楽器の取り扱いについて色々な具体的な注意事項を述べていきます、ほんの少しの知識と心使いが、数多くの事故を避けることになるでしょう。
最近の事例から:
(事例)古いイタリアの楽器(オイルニスが塗ってあった)に、弦楽器専用として販売されている磨きオイル(イダオイル)を使用して、ニスの表面全体が白濁した。(理由と対策)この磨きオイルにはテレピン湯が含まれていると思われ、多用するとニスが溶け、白濁する。こうしたたぐいの商品はよく注意して購入し、多く使いすぎないこと。万一トラブルが起こったら、専門の職人に任せましょう。ミツマにお持ち下さい。
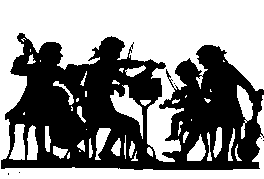
あなたは、ご自分の楽器の鳴りに十分満足されていますか?E線が鳴らないとか、G線が鳴らないとか、G線の音が弱いとか、音色が固すぎるとか・・。もちろん楽器自体の性質によってそれぞれ本来の音色はちがうのですが、駒や魂柱を調整することによって、驚くほど改善されることがしばしばあるのです。そこで、今回は、「魂柱」のお話をしましょう。
魂柱は駒の向かって右足の下に立っていて、右側のf孔からのぞけば見える直径約6mm(ヴァイオリンの場合)の丸い棒です。立っている位置をわずか1mmでもずらすと、楽器の音がずいぶん変わります。魂柱は表板と裏板の圧力だけで立っていて、簡単にずらすことのできる物なのです。あなたの楽器の魂柱の位置はあなた自身の手によって確かめることができます。簡単な方法を書きますと、名刺の厚さくらいの紙切れをf孔から下の図のように魂柱にコツンと当たるまでそっと入れてみて下さい。駒の足からの距離を木目に直角方向と平行方向に計るわけです。
上の図は駒の足と魂柱の位置関係です。図の通り駒と魂柱の間はヴァイオリンの場合約1〜5mm(チェロの場合約5〜12mm)、駒と魂柱の右側が縦に揃っている状態(チェロの場合約5mm外側)が標準的な位置です。
また、魂柱自体の長さをわずかに変えることによっても音が変わります。ときに、魂柱をずらした際、楽器がその魂柱の位置になれるまで日数がかかったりします。魂柱の位置を決めるに当たっては楽器の性格を考慮した上で考える必要があるので一概には言えません。それに楽器の性質も年月とともに少しずつ変わっていきます。ですから理想的な魂柱の位置も変化していくものと考えられます。職人の立場としては、演奏家の皆さんに満足のいく調整をするためには、長年の経験によって鍛えられた耳と、センスが必要な仕事のうちの一つでしょう。
楽器の調整をしていると、時々、魂柱の位置があまりにも悪かったり、表板と裏板にぴったりと合ってなかったり、軸が回ってずれていたり、ひどいときには魂柱の木目の方向を間違って立ててあったりします。そのような魂柱であれば楽器が正常に鳴らないのも当然といえるでしょう。場合によってはきちんと作られていない魂柱を使ったために、表板の裏側が傷ついている楽器を見ることも希ではないのです。魂柱を動かすのはやはり信頼のできる職人に任せた方がよいでしょう。
ご自分の楽器を一度チェックなさってみてはいかがでしょう。
今回は、魂柱についてもっと詳しく知りたいとの要望があったので、少し細かいことを書いてみましょう。魂柱の大切な条件は、位置、長さ、太さ、それに表・裏板との接触面がピッタリあっていることです。
前回にも述べた通り、魂柱の位置によって音が変わりますが、魂柱の長さや太さによっても音は変化します。一般的に、魂柱を駒に近づけると音が大きく硬くはっきりしてきます。逆に遠ざけると柔らかくなりますが音が弱くなり、遠くに響きにくくなります。また、恐ろしく単純にいえば、魂柱をf孔の方にもってくると高音が良く鳴り、中央に近づけると低音が良くでます。この横方向の移動についてはいろんな条件が複雑に関係し、本当は一概には言えないのですが。また、魂柱を長くすると高音が良く鳴るようになりますが音が堅くなります。
魂柱を動かすときに、一つの条件を変えるとほかの条件も変わってくるので、同時にたくさんのことを考慮しなければなりません。また例外も多いのです。と言ったわけで、魂柱を調整するのは、駒や楽器自体の作りを考慮に入れながら、経験とセンスをもって行われなければなりません。楽器も年月によって鳴り方が変わってきますし、演奏家が楽器に対して持つ要求も演奏が上達すると共に変わったりするでしょう。私たちは、弦楽器奏者としての経験を生かしながら楽器を調整していますので、お気軽にご相談下さい。
前回の魂柱に続き、今回も楽器の音色に直接関わってくる重要な部品「駒」についてのお話です。駒には色々な形があり、それぞれに特徴がありますが、今回はそれらの個々について述べることは割愛し、いずれにも共通した基本的で大切なことをお話しします。
まず、駒の位置ですが、左右のf字孔の切れ込みをつないだ線上に駒の足があるのが正しい位置です。そして指板の頭の方からながめて、駒が中央にあり、また表板に対して駒の裏面が垂直に立っていることが必要です。この三方向からの位置確認を絶えず行い、駒がおじぎをしてこないよう注意して、いつも修正する心がけをしてください。駒を少し動かすときは、弦をある程度ゆるめ、弦と表板の間に指を入れ、駒が急にバチンと倒れないように注意しながら、少しずつ修正して下さい。
駒の厚さは、一般的に薄くすれば、高音までリスポンスのいい抜けのいい音になりますが、あまり薄くしすぎると、かえって貧弱な音色になってしまうこともあります。とくに楽器の表板が平坦な(フラットな)楽器ではこの傾向が強いようです。また、駒の材料としては、古くて硬いものが良い結果を生むようです。
私達が駒を製作する際、表面から削りを入れて厚さの調整をしますが、裏面からは削りません。また、駒の足は、楽器の表板にあわせて曲面にピッタリと合うように削ります。駒の頭の曲線や糸溝の幅は、演奏しやすいように作りますが、この微妙なニュアンスは、職人にも演奏家としての経験があれば最高です。
一つ一つの楽器に合わせて入念に作られる駒。変形しないよう、いつもチェックをお忘れなく。
弦にはたくさんの種類があります。楽器の音色は使われている弦によって結構左右されます。しかしあまりにもたくさんの種類があるので、弦選びにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。売られている弦のパッケージを見ると、メーカーや商品名は、大きく書かれていますが、物理的な構造の違いなどはスミの方に小さく、しかも外国語で記されています。初めて見る人や初心者の人にわかりにくいのも無理からぬことです。しかし、弦の特色を知ることは演奏家としての最小限の知識であり、楽器の特性を最大に引き出すためには重要な事です。
弦を構造的な違いから区別していきましょう。弦は大きく分けて、ガット弦(羊の腸で出来ている)とナイロン弦とスチール弦(金属)の3種類に分けることが出来ます。楽器の構造や演奏の形態が時代と共に変化してきたのと同様に、弦も様々な改良がくわえられる事により、色々な種類ができてきました。オリジナルの弦は、裸のガット弦でした。さらに大きな音を出すために金属が回りに巻かれるようになり、そしてスチール弦ができ、さらにスチール弦に金属線を巻いたり、またガットの代わりにナイロンを使用する弦が出現しました。
では、実際に弦を選ぶときはどの様にすればよいのでしょうか? 楽器の特徴や演奏家の腕も、弦を選ぶときに考慮しなければなりません。一般的にヴァイオリンですと(E線以外)年月の経った楽器は、ガット弦の方がより美しい音がでます。しかし、近代の楽器や大きな音を出したい人、また発音の良い音をのぞむ人は、ナイロン弦を使用しています。初心者の場合、ガット弦は湿度や温度に敏感で狂いやすいので、調弦の都合上扱いやすいのは、スチール弦が一番です。チェロの場合は、ガット弦やナイロン弦では音が弱々しくなりすぎるので、スチール弦が好まれています。
具体的に弦のメーカー名と種類の名前を並べてみましょう。一番大きなメーカーであるピラストロ社の場合、オリーヴ(Oliv)とオイドクサ(Eudoxa)がガット弦で、シノクサ(Synoxa)とアリコア(Aricore)がナイロン弦、そしてクロムコア(Chromcor)がスチール弦です。また、ウィーンのメーカー・トマスティーク社の、ドミナント(Dominant)はナイロン弦。スピロコア(Spirocore)はスチール弦です。そのほかにもたくさん弦を作っているメーカーがあります。その上同じ名前の弦でも、太さなどに変化を与えて細かく種類分けされています。例えば、ピラストロのオイドクサのA線は、7種類の太さがあり、(13 3/4)などと書かれているのがそれです。light, dolce, soft, medium, stark, forte, strong と表記されている場合もあります。英語であったりドイツ語であったり、フランス語、イタリア語・・皆さん辞書で調べましょう!
弦について質問がある方や楽器との相性などに疑問がおありの方はいつでもいらして下さい。元演奏家、楽器製作家としてアドヴァイスさせていただきます。ミツマでは各種弦を取り揃え、しかも3割引で提供しています。
最近の化粧品に、コラーゲン配合・・とか、よく耳にするコラーゲン。これは、漢字で書くと膠質。弦楽器の接着剤として使用するニカワのことです。今回は、素肌を美しくもするニカワについてのお話です。
使い捨ての品や工場製の安価な物品が普及した今日では洋の東西を問わず、特に日本では、ニカワはあまり知られていません。また、西洋でも、使われることが少なくなった物の一つでしょう。しかし弦楽器に使われるニカワにはたいへん深い歴史と役割があるのです。皆さんの手元にある弦楽器を子供の玩具にしてしまいたくない人は、よく読んでください。
ニカワの成分はゼラチンです。魚や、動物の皮や骨が原材料です。基本的には同じ物ですが、何から取るかによって、性質が少しずつ違い、対象によって使い分けられたりします。イタリアでは金箔を張るために石膏に使うのは兎の皮のニカワです。楽器の修理には、一般的に骨のニカワ、あるいは魚のニカワでしょう。ケーキを作るために売られているゼラチンが割高になるけれども手に入りやすく、楽器の修理にも向いているので使っている人も多いです。薬屋さんでゼラチンを買うと言った手もあります。わたしはスーパーマーケットで売られてるのと同じものをフィレンツェの画材屋さんで500グラム数百円で買い、いまだに使い切れません。
使い方は一晩ほど水に漬けた後適度に暖めると、コロイド物質ですので流動性があり、冷えるとゼリー、水分を失うとくっつくわけです。弦楽器に使う場合には、一般工芸品の場合より薄めにします。特に表板などよく剥がしたりするところは特に薄く付けてないと次に剥がすときに楽器にひびが入ったりします。安物の楽器などには、濃いニカワがどっさり付けてありますが、本当はよくないことです。ましてボンドを使うのはもってのほかだということがおわかりでしょう。(ときどきこれでわたしは、大変苦労しています・・)
ニカワは、付けたり剥がしたりが自由にできる替わりに、現在一般に使われる接着剤よりも接着力は強くなく、しかも湿度や温度の変化に敏感で、古くなると剥がれやすくなります。もし楽器の接着部分が剥がれたりしたときは、古いニカワをお湯に浸けた、少し硬めの筆で除去した後(木がお湯で濡れてふやけないように注意)、新しいニカワをいれて軽くクランプで締め付けます。そして、はみ出したニカワを乾かないうちにさっと筆で取り除いておくのもこつです。乾いても水でぬらすと徐々にふやけゼリーのようになるので取りのぞくことができます。
基本的にはちっとも難しい作業ではないので、少し練習すれば誰でもできるようになりますが、経験が少ないとちょっとしたことで事故が起こったりするので、やはり専門家にまかせる方がいいでしょう。
「楽器の調整とは何をするのでしょう?」というお便りを頂きました。これをきっかけに、楽器の調整とは何かを考えてみましょう。
まず、最初に言わなければならないことは、どんな弦楽器も木でできているため、長年の間に少しずつ変化し、多かれ少なかれ演奏上の不都合が生じてきます。その時にあわてる事のないように、普段から楽器の正しい知識を修得しておきましょう。まず覚えておいてください。楽器の修理職人をするのに、日本では、どんな許可も資格も必要がないということです。つまり、いつだれでも自分が楽器職人だと宣言すれば、その時から楽器職人なわけです。ですから修理の技術などまちまちです。人のうわさも、どこまで確かなのかわかりません。それではどのようにしたらいいでしょう?
楽器を修理、調整するときは、納得がいくまで内容を尋ねること。難しすぎてわからなかったり、疑問が残っていれば、その日は楽器をもって帰って、本を読む。(できれば、信用のできる英語の雑誌や本を読んでほしい。専門書や"Strings"や "Strad"など。注・日本の雑誌の「ストリングス」ではありません。)あるいは他の修理屋の話を聞いてみるなど、下準備をしてから出直すこともできます。経験豊かで優秀な職人は楽器に対しての知識を惜しむことなく話してくれるでしょう。
元の話に戻りますが、まず、楽器自体の構造にひずみの出てきた場合。例えば、ネックが下がってきたり、ペグの回り方が悪くなってきたりした場合は、ネックを上げたり、駒を削ってあわせたり、ペグを削ってあわせたりします。次に、演奏家の好みによる調整というのがあります。駒のカーブや、駒の高さ、弦の間隔など、演奏家の希望により、ジャストフィットした調整を行うことがあります。この場合、楽器の特性もよく考え、多くの問題が起こらない範囲内で調整を行います。最後に、楽器の可能性をより引き出すための調整というのがあります。例えば、魂柱の位置を変える、魂柱の太さや長さを変える、駒を薄くする、又は厚くするなどといったことです。これには多くの問題点があります。というのは楽器の音を言葉で表現するのは不可能に近く、意志が間違って伝わってしまうこともありますし、また演奏する環境によって音が変わることも考慮に入れなければなりません。そのうえ音の好みは人によってまちまちです。
話がずれますが、日本人はヨーロッパの人々に比べてずいぶん異なった感覚をもっています。もっとも、同じイタリアの中でも地方によって好みの傾向が微妙に違っていたりすることは大変興味深いです。(私は言語 -方言も含めて- にその一因があると確信しています)。私はイタリアでヴァイオリンの演奏家でもあった都合上、友達の楽器の調整を毎日やっていました。彼らはオープンな性格で、機関銃のようにしゃべりまくりますが、建て前がなく本音と冗談を入り交じえた会話なので、とても楽しかった事を今でもなつかしく思い出します。日本では質問しても、仮面をかぶった人が多く、調整しても本当に満足してもらったのだろうか?と疑問に思うことが多く、残念です。というわけで、調整する人の独断と偏見によった調整にならないためにも、演奏者の積極的な主張が必要になります。
ではどのように楽器店を選べばよいでしょう?“私の所にくるのが一番良いです”とお答えしたくなるのですが、それだけではあまり説得力がないので、まず色々数多くの店に行ってみることが必要でしょう。恐ろしいことに日本では閉鎖的なお国柄か、間違った知識があふれてます。先生の言うことを、すなおに受けとめないで、疑問があれば複数の人に質問しましょう、答えがまちまちだったりするでしょうが、その中で間違いを見つけていくことが正しい知識を得ていくうえでの第一歩です。自分の大切な楽器は(財布も含めて)、ひとまかせにせず自分で守るように心がけましょう。
ミツマでは駒を作り替えたり、指板を削りなおしたりするような調整をのぞけば、糸巻や、魂柱を動かしてみるなどといった軽微な調整は無料で行っています。一度立ち寄って下さい。他に友達などの間で質問があれば、遠慮なくご相談下さい。(注)Strings, Strad. は海外のオークションの値段が落札価格が載っていたりします、日本の楽器店ではあまり見かけないようです。ご覧になりたい方は当店にお気軽にお越しください。購入希望の方は直接注文の案内も致します。
ヴァイオリンやチェロの胴体の、ちょうど向かって左のf孔から中をのぞき込むと見える位置に、その楽器の製作者のラベル(フランス語で Etiquette とも言います)が貼ってあるのをご存知でしょう。楽器にラベルを貼る習慣ができたのは16世紀にさかのぼります 。
信頼性はともかくとして、存在しているラベルでもっとも古いものはクレモナの有名なアマティ家のある人物の名前、製作年と製作場所が書いてあります。当時は演奏家や貴族がそのラベルを見てはるばる楽器の注文にやってくるといった重要な宣伝広告の役割をしていました。Cremonaの黄金期と言われている17・8世紀には、著名な作家の楽器は、高い値段で取り引きされるようになってきました。有名なアマティやストラディヴァリやグァルネリなどもこの頃の人です。数多くの偽作品が世の中に出始めたのもこの頃でしょう。Antonio Stradivariの息子 に当たるFrancesco とOmobono も父の死後数多くの楽器に父親のラベルを貼っています。こうしたほうが、楽器が高く売れたからです。
お持ちの楽器のラベルが、本物か偽物かという心配には及びません。楽器の価値を考慮するときには、ラベルは単なる飾りの付属品くらいに考えてください。もっとも、銘器においては本物のラベルが貼ってあるに越したことはないのですが・・。
ときどき偽物のラベルが貼られていることを悪質な行為と受けとめる人もありますが、残念ながら弦楽器のラベルは食品や革製品の品質保証書ではないのです。本来ラベルは楽器の価値を左右するものではなく、弦楽器に関して完全に偽ラベルを取り締まることは不可能です。
著名な楽器には鑑定家によって証明書が付けられることがあります。しかし、鑑定家の間においても真偽の意見の分かれることもあります。ひどいのは、楽器の鑑定をする事自体を商売とし、安易に偽物の鑑定書を作製する人もいます。
自分で楽器の善し悪しを正確に判断できるようになるまでは、高価な楽器には手出しせずに、材料、構造的、音響的に完全で、値段も手頃で、ラベルも正真正銘の現代の優秀な製作家によって作られた楽器で満足しておくことを私はおすすめします。
「優れた楽器には、それぞれの個性と素性の良さを感じさせる品位があり、こうした楽器は演奏上の必要性にも存分に応えてくれるものだ。優れた楽器を見極める眼は、科学者のような精緻な観察力と、楽器の芸術性を受けとめる感性と、そしてそれらを記憶しておくに十分な頭脳と、さらに、実用性を判断できる演奏家としての実力が存在するところに育つのだよ。」と隣で副社長が言っています。さて、次回はいよいよ業界の琴線に触れる「楽器の値段」についてのお話です。
*さらに詳しくラベルの勉強をしたい人のために*
参考文献 ラベルの本 著者:Rene Vannes
題名:Dictionnaire Universel des Luthiers
出版社:Les amis de la musique
値段の安いものですと、通信販売でケース弓付きで19800円のものがあるかと思えば、イタリアの古いものでは、たった1台のヴァイオリンでも1億円を下らない楽器も存在することをご存じだと思います。楽器の値段がどのようにして決まるのかということは誰しも興味を持つことでしょう。一般的に音のいい楽器は、それなりの値段が付いてくると考えられがちですが、必ずしも比例してはいません。安物の楽器でもけっこういい音の出るものもあるのです。音がいいからと言う理由だけで楽器を選ぶと、後でとんでもない楽器をつかまされるはめになることもあるでしょう。
新作の楽器ですと、職人によって本来の伝統的な方法でつくられたヴァイオリンは、1台の製作におよそ160〜200時間必要とします。材料費は、木目の美しさと、寝かせてある年月によって変わります。楽器の値段は製作者の腕の他に、その人の国の事情も影響してくるでしょう。労働賃金の安い、東ヨーロッパや南米又は東南アジアの作家の楽器は安く入る可能性が多いわけです。
古い楽器の場合は複雑です。材木の品質で考えると200年前に切られた木の方が繊維が丈夫で、しかも軽くて楽器として理想的な状態になるため、現代物にはない独特の美しい響きを持った楽器が存在するわけです。ただし注意して下さい、これらは楽器そのものが良く製作されていて、しかも保存の状態が良ければの話です。多くの場合、割れやひびが入って修理されていたり、ニスも塗り直されていたりする事があります。これらの修理は、腕がよくて、正しい知識を持った人たちの手で行われていればいいのですが、必ずしもそうとは限りません。そして最も大切な表板や裏板の魂柱の所にひびが入った楽器、これらの楽器は正しく修理されていたとしても本来の半分程度の価値しかないと考えて良いでしょう。ましてひどい修理がされていたならなおさらです。
あとは芸術作品としての骨董的価値、これが大きく楽器の値段を左右する原因です。実際には状態が悪く、もう使用には耐えなくなっていても、博物館に飾られているような絵画のように、恐ろしく高い値段が付くことも頻繁にあるわけです。こうなってくると、楽器の価値観は人それぞれによって基準が変わってきます。楽器の値段の基準としてよく注目されるのがオークションの落札価格です。オークションの情報はヨーロッパではよく見かけましたが、日本の雑誌では見たことがありません。欧米で演奏家が一般的に読んでいる雑誌のStringsには、毎号楽器のオークションでの落札価格もでています。
19世紀から20世紀にかけて東ヨーロッパでは大量の楽器が量産されています。雑につくられている物が多いのですが、中には結構よくできているものも見かけます。これらの楽器の多くはドイツやイタリアを経由して入ってくるのがほとんどで、入ってきたルートや時代によって値段がいろいろ変化していますが、完全に修理調整された状態で、ほとんどが10万円から30万円ぐらいでしょう。奇妙なことに、日本国内を回っている内に100万以上の値段が 付いていたりすることもあるみたいですが!(次号に続く)
今回は、イチイがイタリアで休暇中のため、副社長が執筆しました。
弦楽器の価値は、ちゃんと勉強しないとなかなかわかりにくいものです。聞きかじりの知識や、うわさばなしでは、大きな間違いをしてしまいます。まず、おおざっぱに楽器の価値を決めるポイントをお話ししましょう。楽器の値段は「音できまる」と思っている人は、しっかり読んで下さい。
まず第一に、楽器の価値の根幹を決めるのは、「生まれ素姓」です。つまり、どこの誰が作ったかということです。名匠の手によるものは高いのです。誰でも知っているストラディヴァリの作った楽器などは、多くの人が欲しがるので、1億円を越える値段だってつきます。作者が腕のいい職人かどうかは、専門の辞典を見ればわかります。
"UNIVERSAL VIOLIN AND BOW MAKERS"という辞典(英語)が入門用に良いでしょう。最近は、楽器製作のコンペティションなどがあり、メダルを取るとプレミアが付き、その作者の楽器の値段もあがります。現代のイタリアの作家の辞典としては、"LIUTAI ITALIANI DI IERI E DI OGGI Vol. 2"(イタリア語)がお勧めです。こういった製作者の辞典は、楽器の「生まれ素姓」を調べるのに必要なので、興味のある方は、購入されると良いでしょう。しかし、楽器の中に貼って有るラベル(エチケットといいます)を頭から信用すると大変なことになります。有名な楽器のラベルは剥がされて盗まれていることがよくあるのです。「鑑定書付きのストラドから、3本のストラドが生まれた。」などという、ジョークがありますが・・。(つまり、鑑定書の付いた偽物のストラド、まるはだかの本物のストラド、本物のラベルの付いた偽物のストラドの合計3本のストラドが世に出回ることになるという意味です。)
私たちは、この楽器は、いつ頃できたものか、どこの国のどの地方でできたものか、どんな製作者の系統をうけついでいるか、製作者の腕はどの程度のものか、楽器そのものの出来具合はいいか、などといったことを中心に楽器の素姓を観察いたします。逆に言うと、例えば、その楽器は、1800年代後半にイタリアのヴェネツィアで、たいへん器用な作家によって作られており、楽器の健康状態も良く・・・などということは、楽器を見ればだいたいわかるわけで、そうすればある程度の価値がわかってくるわけです。古さについては、木やニスの古さ加減等から判断します。産地はニスの色や下地の色、ニスの種類、それから、スクロールに現れる特徴、表板の周囲の処理の仕方、木釘の位置や使い方など、多くのことから判断しますが、イタリアでの修行の跡の見られるドイツの楽器とか、わかりにくいややこしいものもあります。それ以上の特定をしようとすれば、専門的な知識と資料が必要になってきます。
次に、楽器の健康状態が値段に大きく関係します。例えば、裏板や表板の魂柱の当たる部分が割れていないか、バスバーに沿って表板にひびが入ってないか、などは特に値段に関与します。f孔から、歯医者さん用の鏡を使って中を観察するぐらいのことは必ずしましょう。ぱっと見はいいが、結構中はぐちゃぐちゃというものもあります。
勢いにまかせて書いていると、スペースがなくなってしまいました。次号に続きます。
参考文献:1)UNIVERSAL VIOLIN AND BOW MAKERS
(AMATI' PUBLISHING LTD)
2)LIUTAI ITALIANI DI IERI E DI OGGI Vol. 2
(Edizioni LAC)
日本では手には入りにくいので、ご希望の方はお取り寄せします。
![]()
弦楽器の質問箱 (メールで質問をお寄せください)
![]()
〒605-0009 京都市東山区三条通大橋東入ル大橋町102 田中ビル5F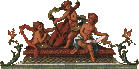 ヴァイオリン製作者の工房
vn@musicinfo.com
ヴァイオリン製作者の工房
vn@musicinfo.com
株式会社ミツマ・ミュージックプロダクツ
TEL. (075)761-1213 FAX. (075)752-5568